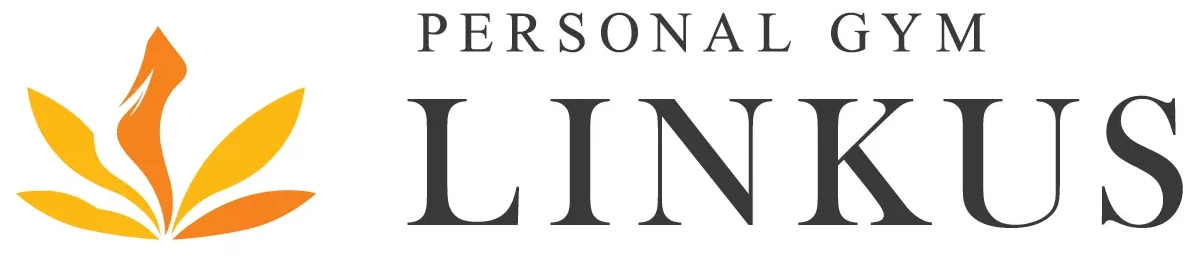甘いものが食べたいときは〇〇不足!甘いもの欲を簡単に抑える方法も解説

ダイエット中に甘いものは控えたいけど食べたい欲が止まらない、やめたいという自分の意思に反して食べてしまうという方は多いと思います。
実は甘いものをやめられない人には共通している原因があり、自分の意志とは関係なしに脳から食べさせられている状態なんです。
脳から甘いものを食べろと言われている状態なので、自分の意思でやめようと思っても絶対にやめることはできません。
しかし、甘いもの欲が止まらない原因さえ解決してしまえば、意思の力なんて関係なく簡単にやめることができるのでストレスなくダイエットが継続できるんです。
本記事では、甘いもの欲が止まらない原因と、甘いもの欲を簡単に抑える方法について解説します。
最後まで見ていただくことで、今まで止まらなかった甘いもの欲が嘘みたいに止まるようになるので、ダイエットが驚くほど捗るようになります。
ぜひ最後までみてください。
筆者が運営するYouTubeでも詳しく解説しているので、動画でサクッと見たい方は下記からご覧ください。
甘いもの欲が止まらない原因
甘いもの欲が止まらないという方はこれから解説する原因に当てはまっていることが多いので、原因を知って解決していけば甘いもの欲は自然と収まってきます。
原因をわからずに無理やり我慢しようとしても絶対に甘いもの欲は抑えられないので、しっかり原因を知って対策していきましょう。
・血糖値が不安定だから
・ビタミンB群、マグネシウム不足
・胃腸が弱っているから
この3つの原因が多く見られるので、当てはまっていないか確認しながら見てみてください。
それぞれについて詳しく解説します。
血糖値が不安定だから
血糖値が不安定というのは、食後に血糖値が急上昇して急降下するような乱高下があり、正常の範囲内に収まっていないということです。
血糖値が乱高下を起こし一時的な低血糖状態を起こすと、脳が糖分を欲するので甘いもの欲が止まらなくなるんです。
食事で糖質をとれば必ず血糖値は上下するんですが、正常の範囲で上下する分にはなんの問題はありません。
ただ血糖値が急上昇するような糖質源を食べてしまうと、そのあと血糖値が急激に下がり低血糖状態を起こして脳がエネルギー不足を感じるので甘いものが欲しくなるんです。
脳は全身に指示を出す司令塔の役割をしていますから、脳のエネルギー不足というのは体にとっては危機的状況です
なので、素早く脳にエネルギーを送るために糖質の中でも吸収の早い砂糖を欲するようになってしまうので、お菓子やスイーツなどの甘いものが欲しくなるということです。
こういった低血糖状態というのは自分が気づかないうちになっていることも多いので普段の生活で次のことがないかチェックしてみてください。
低血糖状態の主な症状
・食後に眠くなる
・朝ごはんを食べないことが多い
・間食の時間に空腹感が強くなる
・ふとしたときに甘いものを食べたくなる
・頭痛や動悸が甘いものを食べて良くなる
こういった症状に心当たりがあるという方は、血糖値の乱高下により低血糖症状が出ている可能性があるので、低血糖を改善する取り組みが必要になるんです。
低血糖を改善することで不思議と甘いもの欲が消え去るという方も多いので、血糖値を安定させる方法を後ほど解説していきます。
ビタミンB群、マグネシウム不足
ビタミンBとマグネシウムは、エネルギーの代謝に関係している栄養素です。
この栄養素が不足してしまうことで上手くエネルギーが作られずに、脳はエネルギー不足を感じてしまいます。
脳のエネルギーは糖質から分解されたブドウ糖で、糖質を分解するときにもビタミンやマグネシウムは必要になるんです。
このときに糖質をエネルギーに変える栄養素が不足していると、うまく糖質を分解できずにエネルギーにすることができなくなります。
そうなると食事や間食で糖質をとって体内に十分糖質はあるのに、脳へのエネルギー供給がうまくいかなくなるので、脳が「まだエネルギーが足りない」と錯覚してしまいます。
またいち早く糖質を摂取しようとして、お菓子などの甘いものが欲しくなってしまうんです。
そして食事で糖質をとって間食でも甘いものから糖質をとってしまえば、さらにビタミンやミネラルの需要も高まります。
お菓子のようにビタミンやミネラルが少ない糖質メインの食材を食べると、糖質が飽和状態になりエネルギーに変換できないので脂肪蓄積の原因にもなるんです。
また、マグネシウムにはインスリンの働きを助ける作用もあり、血糖値をコントロールするときにも重要な栄養素です。
マグネシウムをしっかりとることで血糖値を安定させることができるので、血糖値の乱高下による甘いもの欲を抑えることにつながります。
なので甘いもの欲を抑えるためにはビタミンとミネラルが必要なんですが、不足している方は甘いもの欲が止まらなくなるんです。
胃腸が弱っているから
胃腸が弱っている方は消化力や栄養素の吸収効率が落ちているので、素早く吸収できる糖質を欲するようになるんです。
もともと胃腸が弱いという方もいますが、食生活により後天的に胃腸が弱くなってしまい、それが砂糖依存、甘いもの浴に繋がってしまうケースも多いんです。
胃腸に負担のかかる食べ物
・脂っこいもの
・味の濃いもの
・冷たいもの
・添加物の多いものなど
こういったものは胃腸に負担がかかり消化機能が低下する。
胃での消化力が落ちれば腸でうまくエネルギーが吸収できなくなり、糖質をとっていたとしても体内ではエネルギー不足の状態を作ってしまいます。
そうなると脳が満足しないので、食べているのに甘いもの欲が止まらなくなるんです。
特にジャンクなものを食べているときというのは腸内環境が乱れやすく、栄養素の吸収や老廃物の排泄がうまくできない状態になっています。
どんなに適度な糖質をとっても、効率的にエネルギーを作るためにビタミンやミネラルをとっても、うまく栄養素を吸収できていなければ、エネルギー不足は変わらず脳にとっては食べていないのと変わりません。
なので、普段の食べているもので胃腸が弱っている方は糖質に依存するケースが多く、甘いものが止まらなくなってしまうんです。
胃腸の負担を減らすためには食べるものが重要で、普段の食生活を見直すことが大事です。
脂っこいものや添加物が多いものはなるべく避けるようにして、胃腸への負担を減らしていきましょう。
こういった理由で脳が甘いものを欲しくなっている状態なので、自分の意思だけでは絶対にやめられないんです。
逆に言えば甘いものが欲しくなっている原因をなくすだけで、意思がなかったとしても甘いものは簡単に止められるようになります。
そこでつぎのパートでは、甘いもの欲を簡単に抑える方法について解説します。
甘いもの欲を簡単に抑える方法
甘いもの欲が止まらないのには原因があり、その原因さえ解決してしまえば甘いもの欲はピタッと止まります。
大事なのはエネルギーを作る能力を高めることで、腸内環境が乱れると代謝の低下により、エネルギーの消費効率が落ちてしまいます。
さらに血糖値の乱高下は食欲を増進させるので、血糖値の安定も大事です。
そこで普段の食生活や生活習慣でそういった原因を解決するのが大事なので、そのための方法について解説します。
・食物繊維を含む炭水化物をとる
・腸内環境を整える
・睡眠時間を確保する
この3つを意識することで甘いもの欲を驚くほど解消できるので、ぜひ意識して生活してみてください。
それぞれについて詳しく解説します。
食物繊維を含む炭水化物をとる
ダイエットで食事制限をしているとエネルギー源である糖質が不足してしまい、低血糖状態を作り甘いもの欲につながります。
しかし不足している糖質を補うために、血糖値が急激に上がるような糖質源である白米、食パンなどを食べすぎてしまうと、血糖値の乱高下により低血糖状態を作ってしまいます。
そこで、食物繊維を多く含む炭水化物源を食べることで十分な糖質を摂取することができて、血糖値の乱高下も防げるので糖質への依存が減って甘いもの欲もなくなるんです。
食物繊維をしっかり摂取すると一緒に食べたものをゆっくり吸収していくようになるので、糖質の吸収も緩やかになり血糖値が安定します。
血糖値が安定することで脂肪合成ホルモンのインスリンの過剰分泌を抑えることもできるので、体脂肪の蓄積も抑えます。
血糖値の乱高下は甘いもの欲を増やすだけではなく空腹を感じやすくなるので、血糖値を安定させることで空腹感が減って食べ過ぎを抑えることも出来るんです。
食物繊維を含む糖質とは玄米、もち麦、全粒粉パンなどの茶色の炭水化物や、さつまいも、かぼちゃなども食物繊維が豊富なのでおすすめです。
食物繊維の多い炭水化物を増やすには
・白米を玄米やさつまいもに変更する
・白米にもち麦を混ぜるなど
これだけでも食物繊維が増えて血糖値が安定する
さらに食物繊維を含む糖質の特徴として、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素が豊富な点があります。
ビタミンやミネラルを十分にとってエネルギーの消費効率を高めることで、糖質への依存度も減るので甘いもの欲を抑えることにつながるんです。
なので私は普段から玄米にもち麦を混ぜて、食物繊維やビタミン、ミネラルをしっかり取るようにしていて、甘いもの欲を抑えるようにしています。
いつも白米を食べているという方は、朝食に食物繊維を多く含む炭水化物源をとることで、一日の甘いもの欲を抑えることにつながるので朝食に取り入れることをおすすめします。
腸内環境を整える
腸内細菌のバランスというのはその人の食欲や食の好みに大きく関係していると言われていて、腸内環境を整えることで甘いもの欲も収まるんです。
腸内細菌の善玉菌が優位になっていると腸内環境がいい状態なんですが、善玉菌は発酵食品や食物繊維などの体にいい食材が大好きです。
逆に悪玉菌が優位になっている腸内環境が悪い状態であれば、悪玉菌の好物であるジャンクフードやお菓子などの甘いものが欲しくなるんです。
なので腸内環境を整えることで善玉菌が優位になり自然と健康的な食材を欲するようになるので、甘いもの欲がなくなるということです。
さらに、栄養素の吸収のほとんどは腸内で行われているので、腸内環境を整えることで栄養素の吸収がスムーズに行われるようになっていきます。
食べたものをしっかり吸収できるようになれば必要以上に脳が栄養を欲することがないので、食欲も安定しやすいです。
そして、エネルギーを効率的に生み出すことができるようになるので、糖質への依存度が減って甘いもの欲がなくなります。
腸内環境をよくするための一番の方法は、食物繊維と発酵食品を食べることです。
食物繊維や発酵食品をとることで善玉菌そのものを増やしつつ、善玉菌の餌も同時にとることができるので超効率的に腸内環境を整えることが出来るんです。
①食物繊維の多い食材
・玄米
・オートミール
・もち麦
・そば
・きのこ類、海藻類、葉物野菜など
②発酵食品
・納豆
・味噌
・キムチ
・ヨーグルトなど
納豆ご飯やわかめのお味噌汁、間食にヨーグルトを食べたりして、1日通して食物繊維と発酵食品を食べるようにしましょう。
睡眠時間を確保する
睡眠と食欲というのは密接に関係していて、甘いもの欲を抑えるためにも睡眠時間は重要なんです。
そして脳腸相関といって脳と腸の状態はお互いに影響し合っているので、睡眠時間をしっかり確保して脳の疲れをとることで腸内環境を良くすることにもつながるんです。
逆に睡眠時間が短く脳のメンテナンスができないと、それが腸に影響して腸内環境の悪化につながり甘いもの欲を増やすことにもつながるんです。
さらに、寝ている間に食欲に関係するホルモンが分泌されていて、しっかり寝ている人は食欲を抑制するホルモンが優位になります。
逆に睡眠不足の人は食欲を増進させるホルモンが分泌されるので、睡眠時間によって食欲が大きく変わるんです。
実際の研究で
・8時間睡眠の人と比べて5時間睡眠の人を比べた場合
→5時間睡眠の人は食欲増進ホルモンが14.9%増えて、食欲抑制ホルモンが15.5%も減ったというデータがある
※4時間睡眠になると食欲増進ホルモンが28%も増えて、お菓子やジャンクなものを食べる傾向が強くなったと言われている。
ただ睡眠時間が短いだけで脳が疲労を感じてしまい、早くエネルギーを補給するために甘いものを欲するようになってしまうんです。
なので、甘いもの欲が止まらないという方は睡眠時間がしっかりとれているか、深い眠りに入っている質の高い睡眠になっているかを確認しましょう。
まとめ
以上が、甘いもの欲を簡単に抑える方法3選でした。
甘いものを欲するのは脳からの命令なので、自分の意思ではコントロールすることができません。
我慢や気合、根性でやめようと思っても、ストレスを溜めるだけでやめるのはかなり難しいです。
自然と甘いものがやめられるように、ぜひ本記事を参考に実践してみてください。
そして最後にお伝えしたいことは、甘いもの欲をなくすための方法をお伝えしましたが、この3つだけが全ての原因ではないということです。
一番は普段の食生活で栄養バランスのとれた食事をとることが大事で、必要な栄養素がとれることで甘いもの欲はなくなっていきます。
あくまでも本記事の方法は応急処置のようなものなので、1日3食できちん栄養バランスを整えて甘いもの欲を抑えていきましょう。
しかし、自分では食事のコントロールができないという方も多いと思います。
そんな方には、パーソナルジムに通ってみることをおすすめします。
筆者が運営しているパーソナルジムLINKUS秋葉原店では、体験トレーニングを募集しております。
体験枠は埋まりやすくなっているため、下記からお早めにお問い合わせください。